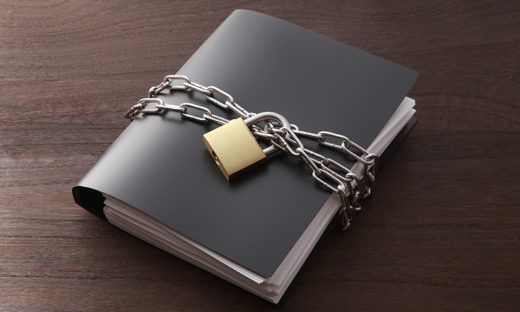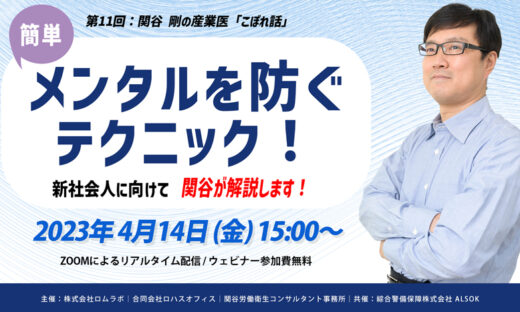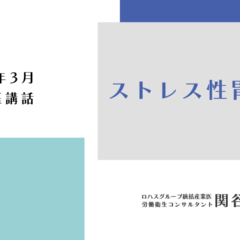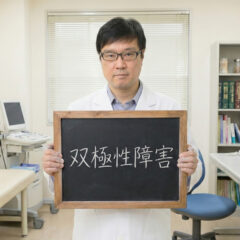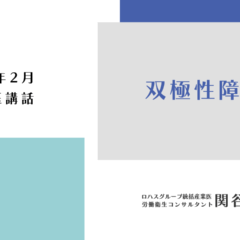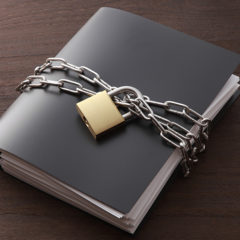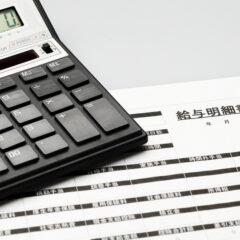職場のハラスメント対策〜健全な職場環境を作る〜

統括産業医の関谷です。
健康的な職場環境を作るためには、精神的ストレスの発生を防ぐことが重要であると思います。職場でのストレス要因の1つとして上げられるのがハラスメントです。ハラスメントは、パワハラやセクハラだけに留まらず、マタニティハラスメントやリモートハラスメントなど年々増え続け、現在では50種類を超えているとされています。様々な種類が存在し問題視されていますが、「知らなかった」「そんなつもりではなかった」では許されないのがハラスメントです。
男女雇用機会均等法が改正された平成29年1月から、職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの 防止措置を講じることが、事業主に義務付けられました。 令和2年6月には初めてパワハラを禁止する法律として労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が 大企業の事業主に先行して義務付けられ、令和4年4月からは中小企業の事業主にも義務付けられた ことにより、すべての企業にパワハラ防止法に基づくパワハラ防止措置を講じる事が義務付けられました。
そして今年6月11日にカスタマーハラスメント(カスハラ)と、求職者等に対するセクハラ(いわゆる「就活セクハラ」)に関する法律改正(令和7年法律第63号)が公布されました。この改正により、カスハラや就活セクハラの防止措置が事業主の義務となります。今回の法改正で事業所として新たに対策が求められるハラスメントに対して、認識を深めるようにして下さい。
1:今回の法改正とは?
■全企業が対象の義務化■
カスハラ(取引先やお客様からのハラスメント)や就活セクハラ等のハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法等が今年6月に改正されました。公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日に施行予定で、一部の規定は令和8年4月1日に施行予定となっています。
カスハラと就活セクハラを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となっており、施行は1年半後ですが、これらのハラスメントは、いつ発生してもおかしくない問題ですから、今から事業所として法令で対策が義務化したことを全従業員に周知するようにしましょう。
2:カスハラ対策とは?
ハラスメント対策という観点では、既に義務化の対象となっているパワハラやセクハラと基本的な要素は変わりませんが、カスハラが発生する状況は特有の要因がありますから、他のハラスメントと共通する点、異なる点を理解して対策を考えてください。
カスハラとして認定される要素は、他のハラスメントと類似していますが、大きく3つあり、下記のすべてを満たすとカスハラと認定されます。
【1】顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う
【2】社会通念上※許容される範囲を超えた言動により
【3】労働者の就業環境を害すること
※社会通念上というのは、具体的に何を指すかと言えば、法律の枠で考えれば順守しているが、社会的にはおかしい行為、常識を超えた行為のことです。例えば、取引先やお客様に迷惑を掛けるようなことが発生して、相手から「土下座をして謝れ!」と怒鳴られたとしましょう。土下座をやらせることが違法になるかはかなり判断が難しいですが、社会通念として捉えると逸脱している行為と言えるでしょう。つまり、土下座という行為を取引先やお客様が求めて来たら、それはカスハラと認められますから、事業所として対応することが求められる事案となります。
■事業主が講じるべき対策■
カスハラはサービス業では多くのお客様と直接接する機会もあり、カスハラの被害を受けた従業員が退社するような事例から、一定の対策は部署単位では構築されていると思いますが、今後は事業所としてのルール作りやマニュアル作成が求められています。
忘れがちなのは、カスハラでは自分達がハラスメントの加害者になってしまうことです。自社の従業員が他社の従業員に対してカスハラ行為をしたり、発言したりする可能性があることも視野に入れて、加害者にならないようなハラスメント対策も講じるようにしましょう。
そして、カスハラ被害にあった場合、相談できる専門の窓口を事業所内で設置するようにしましょう。直属の上司に相談するだけでなく、事業所としての対策が義務化されるわけですから、会社として専門の相談窓口を設けて全従業員に知らせることが求められます。また、カスハラが発生した時に事業所として迅速に対応出来るように、マニュアル作りや体制構築は整えておきましょう。
3:就活セクハラへの対策
求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対しても、セクシャルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
■就活セクハラとは何か?■
就活セクハラとは、応募する企業やその採用担当者が優越的な立場を利用して就職活動中やインターンシップ中の学生に行うセクハラやパワハラなどのことです。厚生労働省の「令和2年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」によると、就職活動中の学生の4人に1人が就活セクハラの経験があるそうです。
働いている人に対するハラスメント等の問題は、労働法という法律で対処出来ます。しかし、就職する前の学生という立場では、労働法の対象者にはならず、これまでは直接的な解決策がありませんでした。
セクハラの範疇として、採用担当者という立場を利用した食事や飲酒の強要などだけでなく、選考過程中の会話の中でも、性差別を示す発言をすることが対象となります。例えば、「女性だからこうだ」「男性はこうしなければいけない」という発言は性差別に該当します。
■未然に防止するための方法■
就活セクハラに限らず、ハラスメントの基本要因はセクハラやパワハラと同じですから、まずはハラスメントに対しての認識や対応について、セミナーや講習会を全従業員に対しておこなうようにしましょう。
就活セクハラでも義務化に伴い、事業主の方針の明確化及び周知・啓発と、相談体制の整備と周知が求められており、発生後の迅速かつ適切な対応(例:学生からの相談への対応、被害者への謝罪等)も含まれます。
就活セクハラに関する事業主が講ずるべき具体的な措置の内容等については、今後厚生労働省が指針において示す予定としており、遠からずガイドラインが出されると思われます。
これらハラスメントに関する国、事業主、労働者、顧客等(カスタマーハラスメントの場合)の責務も明確化することを政府は表明しており、ハラスメントは行ってはならないものであり、働く人に対する言動に注意を払うように努めるものとしています。
ハラスメントは被害者を減らすという発想よりも、加害者を無くしていくことが求められていますから、事業所内でも組織全体の認識と共に、従業員個人でもハラスメントをおこさないように講習会への参加等に努めて下さい。
4:職場のハラスメント対策で参考になるサイト
厚生労働省 「令和7年の労働施策の総合的な推進」
厚生労働省では「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」というタイトルで、ホームページ内に専用ページを設け、概要資料やリーフレット等のダウンロードが出来るようにしています。今後、この法律に関しての新しいガイドラインなどもこのページで発表があると思われますから、事業所内でカスハラと就活セクハラについて取り組む際は、御覧下さい。
東京都産業労働局 企業支援ナビ「TOKYOノーハラ」
東京都では企業のハラスメント防止対策への理解促進・取組支援を図るため、「TOKYOノーハラ」サイトを立ち上げました。企業規模にかからわずしっかりと対策に取り組むことは、自社の社員を守るだけでなく、快適な職場環境があることで社内外からの評価も向上し、“優秀な人材が集まる”“新たな事業の芽が育つ”といった会社の成長戦略にもつながるはず、という狙いで開設されています。多様なハラスメントの紹介や東京都の相談窓口の場所や開設時間についても詳しく書かれています。
内閣府男女共同参画局 女性応援ポータルサイト
内閣府の男女共同参画局が、子育て・介護、仕事、健康等に関する政府の支援策やサービスといった、女性に役立つ情報を掲載する「女性応援ポータルサイト」を開設しています。この中には「安全・安心な暮らしをしたい」という項目の中に、「ハラスメントのない社会づくり」というページがあり、都道府県の労働局雇用環境・均等部(室)の連絡先や、女性の人権ホットラインの連作先なども掲載されています。
あかるい職場応援団(厚生労働省サイト)
職場のパワーハラスメント問題の予防・解決に向け、問題に関する様々な情報発信を行なっていくため、厚生労働省委託事業として、「あかるい職場応援団」は平成24年10月1日に開設。ハラスメント基本情報では様々なハラスメントの種類や定義をイラスト入りで分かりやすく書かれており、SNSも開設しています。
厚生労働省 企業向け「就活セクハラ対策」 特設ページ
就活セクハラ対策に対してどう対処すれば良いか、厚生労働省では企業向けと学生向けで別々に専用サイトを開設しています。就活セクハラが発生しない状況を作るための事業所の対策が書かれており、対策を講じている企業の実例集のダウンロードも出来ます。
学生向け「就活セクハラ対策」はこちら
YouTubeチャンネル「関谷剛の産業医こぼれ話」 2025年8月『職場のハラスメント対策』
医師・産業医の関谷剛先生が、この通信と同じテーマについて解説した動画を毎月公開しております。文章だけでは伝わりにくい、病気予防のポイントや産業医としての経験談などを自らの言葉で説明しています。YouTubeチャンネルで御覧頂けますから、事業所でもご家庭でもぜひ御覧下さい。
あとがき
新入社員や中途入社等の新規雇用社員にハラスメント防止を徹底させるには、就業規則に記載しておくことも重要です。今回の様な国によるハラスメント対策の義務化を受けて、就業規則を手直しする場合は、社労士と共に産業医にもご相談ください。(産業医 関谷剛)