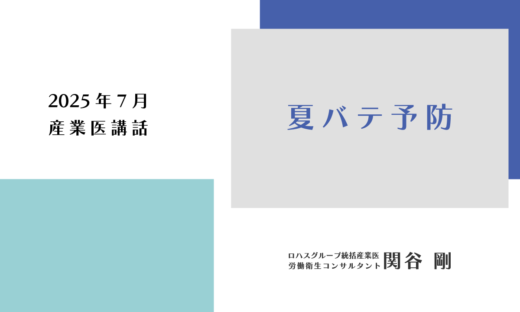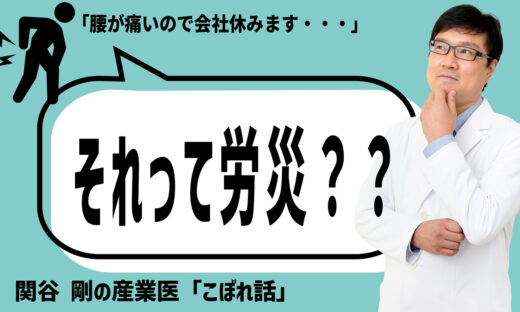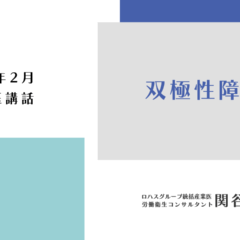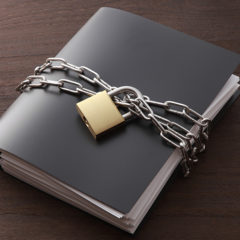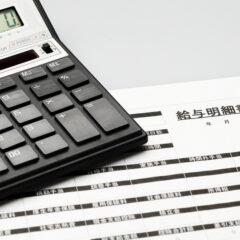睡眠の質を上げるコツ〜良い睡眠が健康を支える〜

統括産業医の関谷です。
夏の猛暑もひと段落し、10月に入ると気温が下がるため、夜はクーラーを使わなくても快適に眠りやすくなってきたと思います。以前から繰り返してお伝えしていますが、睡眠は運動と食事と並んで、人間の健康維持には欠かせない三大要素の一つです。運動や食事に気を付ける人は沢山いますが、睡眠の質を上げるために行動している人は少ないように思います。
最も重要な休養行動である睡眠の質を上げることは、毎日の健康を支え、仕事への集中度合いも高められます。質の良い睡眠を確保するためには、いくつかのポイントがあります。自分自身のため、事業所で働く同僚のためにも、この機会に睡眠の質を上げるコツを学んでみてください。
<1>睡眠の基本的な特徴
■必要な睡眠時間は年齢によって変わる■
夜間に実際に眠ることのできる時間は、加齢により徐々に短くなることが、脳波を用いて厳密に夜間の睡眠時間を調べた研究で示されています。15歳前後では約8時間、25歳で約7時間、45歳では約6.5時間、65歳では約6時間というように、成人後は20年ごとに30分程度の割合で夜間の睡眠時間が減少します。
通常ライフステージごと(こども、成人、高齢者)に睡眠に関する推奨事項は厚生労働省などでまとめられていますが、このページでは主に成人に十分な睡眠を確保するための情報を紹介しています。
また、睡眠時間は季節によっても変動し、夏季に比べて冬季に10〜40分程度、睡眠時間が長くなることが分かっています。さらに睡眠には少なからず個人差(健康状態、身体機能、生活環境等)があること、持病等によっても睡眠の状態が変化する可能性があることを十分に認識してください。ここに書かれている内容は、すべての成人に必ず当てはまるわけではありません。さまざまな要因があることを理解したうえで、睡眠の質を上げるコツを参考にしてください。
<2>睡眠休養感を高める
睡眠には1日の活動で蓄積した疲労やストレスから回復させる重要な役割があるため、睡眠休養感(睡眠で休養がとれている感覚)を向上させることを目指しましょう。睡眠時間は長すぎても短すぎても健康を害する原因となり、成人では6時間以上の睡眠時間が適正とされています。日常生活の習慣を改善して睡眠時間を確保し、睡眠休養感を高める工夫を日常生活に取り入れましょう。
■就寝前にデジタル機器は使わない■
仕事でもプライベートでもノートパソコン、タブレット端末は欠かせない道具となっており、スマートフォンに至っては風呂場やトイレにも携帯して使用するのが当たり前になっています。しかし、これらデジタル機器は寝室には持ち込まず、電源を切って、別の部屋に置いておきましょう。
近年のスマートフォンにはLEDが使用されており、体内時計への影響が強いブルーライト(短波長光)が多く含まれているため、寝室にはスマートフォンやタブレット端末を持ち込まず、できるだけ暗くして寝ることが良い睡眠に寄与します。特に、寝そべりながらデジタル機器を使うと、ディスプレイの視聴距離が近くブルーライトを浴びやすくなるため、寝つきや睡眠の質の悪化につながります。
心地よい睡眠がとれる寝室にする
良質な睡眠を確保するためには、寝室の環境を整えることが大切です。この場合の環境とは「光」「音」「温度」「湿度」、そして「寝衣・寝具」も含まれます。
睡眠中の寝具内の環境は、温度は33℃前後、湿度は50%前後が良いとされています。衣服や寝具で寝具内の温度は調節できるので、低い温度への幅は広く、室温としては13~29℃が許容範囲とされています。なお、同じ温度の環境下では湿度が高いと覚醒しやすくなり、深い睡眠が得られにくくなることが報告されていますから、寝室は高湿度にならないようにしてください。
睡眠中は40dBA(デシベルエー)以下の音環境が望ましいとされており、50dBA以上になると半数の人は睡眠が阻害されると言われています。40dBA以下の音の目安としては図書館や木の葉の触れ合うくらいの音量です。50dBA以上の音は、換気扇や家庭用クーラーの室外機の音、テレビや洗濯機などの生活機器が発する程度の音量です。夜眠るときは、できるだけ外部の騒音を遮断し、テレビやラジオを消すなど、睡眠中の覚醒を促す刺激を減らしましょう。
<3>生活習慣の改善
朝の光を浴びることは体内時計の調整に役⽴ちますが、朝食も同じく体内時計の調整に効果があります。1週間ほど朝食を取らない状態が続くと、体内時計が遅れることが報告されています。朝食を抜くと体内時計の遅れによって寝つきが悪くなり、睡眠不足になりやすくなります。朝食が睡眠休養感の低下と関連することも、最近の調査研究で明らかにされています。
■就寝前の飲食や行動■
就寝前の夜食や間食は、朝食の欠食と同様に体内時計を後退させ、翌朝の睡眠休養感や主観的睡眠の質を低下させることが報告されています。さらに、夜食や間食の過剰摂取は、糖尿病や肥満をもたらし、閉塞性睡眠時無呼吸の発症リスクも高めることが報告されています。
スムーズに入眠するためには、リラックスして脳の興奮を鎮めることが大切です。そのためには、寝る前には少なくとも1時間、家事や仕事、勉強から離れてリラックスする時間を持つことをおすすめします。
■適度な運動の効果■
睡眠は、日中の身体活動等で消耗した体力等の回復の役割を担うことから、日中の身体活動量・強度が、眠りの必要量や質に影響します。また、運動習慣がない人は、睡眠休養感が低いことがわかっています。そのため、適度な運動習慣により日中に身体をしっかり動かすことは、入眠の促進や中途覚醒の減少を通じて睡眠時間を増やし、睡眠の質を高めることにつながります。
睡眠は深部体温リズムと深く関わっています。運動で深部体温が上昇した後、全身の血液循環が高まり、放熱が促進され、深部体温が下がります。この深部体温が下がる機序を利用するのが睡眠改善のコツです。
運動のタイミングとしては、日中に運動を行うことで、身体活動量を確保しやすくなるとともに、寝る直前まで興奮状態が続くことを避けることができます。夕方や夜の時間帯の運動でも(目安:就寝2~4時間前まで)、睡眠改善に有効であることが報告されています。運動の頻度は週1回よりも複数回行う方がより効果的ですが、まずは運動習慣を確⽴することが大切です。
心身のリラクゼーションは、良い睡眠をとるために重要な要素ですが、嗜好品は使用量や使用時刻(タイミング)などを誤ると、睡眠を悪化させ、健康に有害な場合があります。
カフェインは覚醒作用を有するため、寝つきの悪化や中途覚醒の増加、眠りの質を低下させる可能性があります。アルコールは長期間続けて飲むと、依存や耐性が生じ、やめたときに眠れなくなることがあります。また、大量のアルコール摂取や毎日の飲酒は推奨できません。たばこに含まれるニコチンは覚醒作用を有しており、睡眠前の喫煙は、入眠潜時の延長(寝つきの悪化)、中途覚醒の増加、睡眠効率の低下、深睡眠の減少をもたらします。
<4>睡眠で参考になるサイト
厚生労働省 健康日本21 アクション支援システム~健康づくりサポートネット
厚生労働省は睡眠・休養分野の取組をさらに推進するため、健康づくりに寄与する睡眠の特徴を国民にわかりやすく伝え、より多くの国民が良い睡眠を習慣的に維持するために必要な生活習慣を身につける手立てとなることを目指し「健康づくりのための睡眠ガイド2023」を策定しました。睡眠ガイド2023に沿った睡眠の悩みを解消する方法や、ぐっすり眠ってすっきり目覚めるためのコツをこのサイトで紹介しています。
東京都保健医療局 とうきょう健康ステーション 眠り方改革してみませんか?
東京都生活文化局が平成28年に実施した調査によると、30歳代から50歳代の働く世代の都民の約半数が「睡眠が不足している」と感じていることが分かりました。そこで、働く世代の方々を対象に、睡眠に関する正しい情報を提供するページ「眠り方改革してみませんか?」を、とうきょう健康ステーションのサイト内にを設けています。ここでは、眠り方のコツの紹介や、パネル・パンフレット・ポスターなどの啓発資料のダウンロードもできます。
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 睡眠休息感がカギを握る
YouTubeチャンネル「関谷剛の産業医こぼれ話」 2025年10月『睡眠障害』
医師・産業医の関谷剛先生が、この通信と同じテーマについて解説した動画を毎月公開しております。文章だけでは伝わりにくい、病気予防のポイントや産業医としての経験談などを自らの言葉で説明しています。YouTubeチャンネルで御覧頂けますから、事業所でもご家庭でもぜひ御覧下さい。
あとがき
睡眠環境や生活習慣、嗜好品の摂取方法を改善しても睡眠休養感が高まらない場合、不眠症や閉塞性睡眠時無呼吸症、うつ病などの睡眠障害が隠れている可能性があります。気になる方は、産業医に相談してください。(産業医 関谷剛)