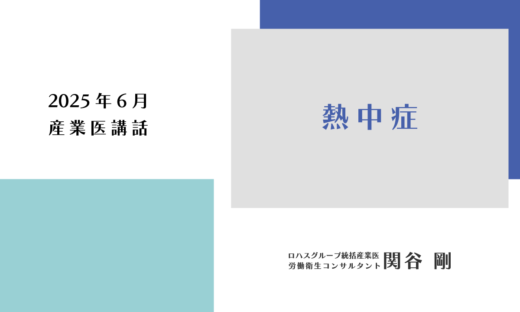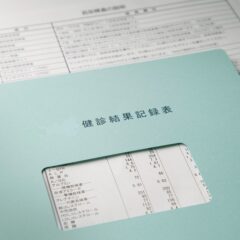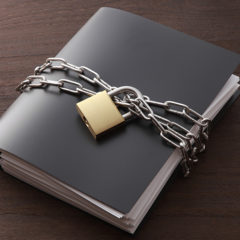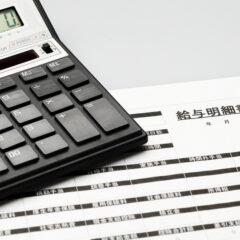年末年始の暴飲暴食を防ぐ〜健康的な飲酒量とは〜

統括産業医の関谷です。
年末の仕事納め前に忘年会を開くのは、欠かせない恒例行事となっている会社も多いと思います。消防庁の統計によれば、急性アルコール中毒で救急搬送された人が1年のうち最も多いのは12月です。その主な理由は、忘年会などでの過度の飲酒によるもの考えられています。
政府では不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となることから、アルコール健康障害対策基本法を2014年6月に施行しました。この法律では、国民が広くアルコール関連の問題について関心を持ち、理解を深めることを目的として、毎年11月10日から11月16日までを「アルコール関連問題啓発週間」と定めています。
自社だけでなく取引先との忘年会や新年会など、年末年始は飲酒の機会が増えます。社員の健康を守るためにも、飲酒による健康リスクについて知り、忘年会があっても飲み過ぎに注意することが大切です。そのために、医学的な最新の知見を学びましょう。
1:飲酒に関する最新ガイドライン
■適切な飲酒量と飲酒行動■
2010年5月にWHO(世界保健機関)が採択した「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」を受け、2013年12月にアルコール健康障害対策基本法が国会で成立しました。
この法律の施行に合わせて、厚生労働省はアルコール健康障害対策推進基本計画を策定しました。また、飲酒によるリスクについての知識を広めるために、国民一人ひとりが適切な飲酒量や飲み方を判断できるように「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を2024年2月に公表しました。
このガイドラインは、飲酒による病気や行動面でのリスクを分かりやすく説明しています。そのうえで、どれくらい飲むのがよいかや、安全な飲み方、気をつけるべきポイント(避けるべき飲酒など)を示しています。これによって、飲酒する際や飲酒後に適切な判断ができるようになることを目的としています。
2:飲酒量の目安
飲酒においては、お酒が含まれる飲み物の容量(ml)ではなく、その中に含まれる「純アルコール量(g)」について注目することが大切です。
お酒に含まれる純アルコール量は、 「摂取量(ml)×アルコール濃度(度数/100)×0.8(アルコールの比重)」という計算式で求めることができます。そのため、純アルコール量は食品のエネルギー(kcal)のように数値で把握できます。
摂取量(ml) × アルコール濃度(度数/100)× 0.8(水との比重) = 純アルコール量
[ビール ロング缶] 500ml(5%)の場合 : 500(ml) × 0.05 × 0.8 = 20(g)
[日本酒 徳利2本] 2合(15%)の場合 : 360(ml) × 0.15 × 0.8 = 43.2(g)
[ワイン1本] 750ml(12%)の場合 : 750(ml) × 0.12 × 0.8 = 72(g)
お酒を飲むときは、どれだけの純アルコール量が含まれているかを知り、自分が飲む量をきちんと把握しましょう。これにより、病気のリスクを減らすための目安が立てやすくなり、健康管理にも役立ちます。
■アルコールの代謝は人によって変わる■
飲酒した際、飲んだお酒に含まれるアルコールの大半は、小腸から吸収され、血液を通じて全身を巡り、肝臓で分解されます。アルコールの分解には、体内の分解酵素と呼ばれる物質等が関与していますが、体質的に分解酵素のはたらきが弱いなどの場合には、少量の飲酒で体調が悪くなることもあります。
飲酒による影響には個人差があり、例えば年齢、性別、体質等の違いによって、それぞれ受ける影響が異なります。
女性は一般的に、男性と比較して体内の水分量が少なく、分解できるアルコール量も男性に比べて少ないことや、エストロゲン(女性ホルモンの一種)等のはたらきにより、アルコールの影響を受けやすいことが知られています。そのため、女性は男性に比べて、少ない量や短期間の飲酒でもアルコール関連の肝硬変を発症する場合があります。このように、女性のほうがアルコールによる身体への影響が大きく現れることがあります。
3:飲酒量と発症リスク
■泥酔によるリスク■
過度なアルコール摂取により運動機能や集中力の低下等が生じ、高所での作業による事故などの発生、飲酒後に適切ではない行動をとることによっての怪我や他人とのトラブル(路上や公共交通機関でのトラブル、暴力行為等)、紛失物の発生(金銭等や機密書類、ノートパソコンやUSBメモリ等の紛失)などが考えられます。
高齢者は、若いころと比べて体内の水分量の減少するため、同じ量のアルコールでも酔いやすくなります。また、飲酒量が一定量を超えると、認知症を発症する可能性が高まります。あわせて、飲酒による転倒・骨折、筋肉の減少(サルコペニア等)の危険性が高まります。
■過度な飲酒が引き金になる病気■
急激に多量のアルコールを摂取すると急性アルコール中毒(意識レベルが低下し、嘔吐、呼吸状態が悪化するなど危険な状態)になる可能性があります。また、長期にわたって大量に飲酒をすることによってアルコール依存症、生活習慣病、肝疾患、がん等の疾病が発症しやすくなります。
たとえば、高血圧や男性の食道がん、女性の出血性脳卒中については、少量の飲酒でも発症リスクが高まることが分かっています。一方、大腸がんでは、1日あたり20g(週150g)以上の飲酒を続けると、発症リスクが上がるとする研究結果があります。
最新の研究により、病気ごとに発症リスクが高まる飲酒量(純アルコール量)が明らかになっています。「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」では、この飲酒量(純アルコール量)が男女別にリスト化されています。「4:飲酒量で参考になるサイト」から確認してみてください。
飲酒をするときのさまざまな危険を避けるために、ガイドラインでは次のような配慮が紹介されています。
①自らの飲酒状況等を把握する
②あらかじめ量を決めて飲酒をする
③飲酒前又は飲酒中に食事をとる
④一週間のうち、飲酒をしない日を設ける
4:飲酒量で参考になるサイト
厚生労働省 アルコール健康障害対策
アルコール健康障害対策基本法が成立した後、基本法に基づき2016年5月に「アルコール健康障害対策推進基本計画」を厚生労働省で策定、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進しています。「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」もこのページからダウンロードすることができます。
東京消防庁 命に関わることもある「急性アルコール中毒」
東京消防庁のサイトで、急性アルコール中毒にまつわる救急活動の傾向とともに、安全で楽しいお酒を飲むための注意点や、万が一の事態に遭遇した時の応急処置方法などを紹介しています。
東京都保健医療局 健康ステーション「飲酒」
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 依存症対策全国センター アルコール健康障害対策基本法について
NHK きょうの健康 知っておきたい!飲酒に関するガイドライン
YouTubeチャンネル「関谷剛の産業医こぼれ話」 2025年11月『年末年始の暴飲を防ぐ』
医師・産業医の関谷剛先生が、この通信と同じテーマについて解説した動画を毎月公開しております。文章だけでは伝わりにくい、病気予防のポイントや産業医としての経験談などを自らの言葉で説明しています。YouTubeチャンネルで御覧頂けますから、事業所でもご家庭でもぜひ御覧下さい。
あとがき
飲酒の影響を受けやすい体質の人は、より少ない量の飲酒(純アルコール量)にとどめることが望ましいです。アルコールによる影響は、病気や臓器の状態、また個人差によって異なります。自分に合った飲酒量については、産業医に相談することをおすすめします。(産業医 関谷剛)