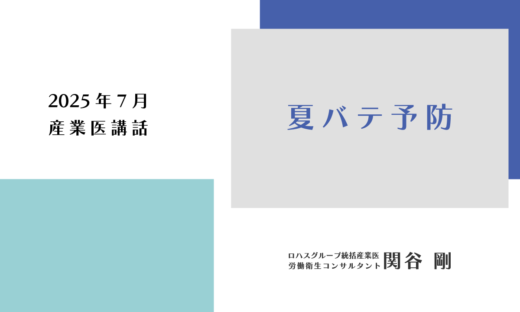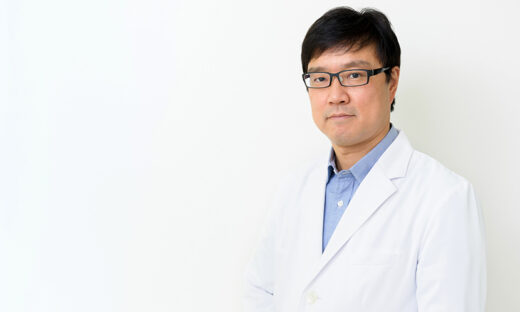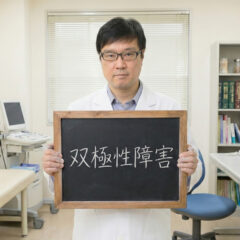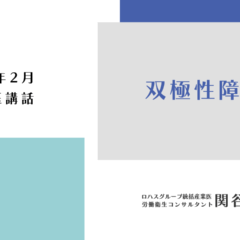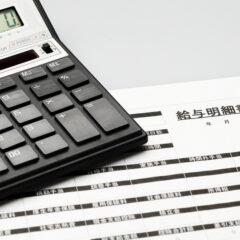インフルエンザはなぜ怖いか?〜今年の傾向と基本的な対策〜

統括産業医の関谷です。
猛暑だった8月、新型コロナウイルスの感染者数が増加し、全国平均では今年1月の冬と同じくらいの感染者数が報告されました。自治体によっては、冬場よりも感染者数が多い地域もありました。暑い夏に感染症が広がったことに驚かれた方も多いのではないでしょうか。新型コロナウイルスが全世界で拡がった際には、熱帯地域であるインドやパキスタンでも夏に多くの感染者が発生しました。つまり、感染症は夏でも感染する可能性があり、さらに冬に入る前から準備しておく必要があることを示しています。
コロナウイルスによる混乱が終わったと安心して対策を怠ると、今年の冬には感染症が大流行する可能性があります。医師・産業医として、皆様に改めて感染症への注意を呼びかけ、今の時期から事業所としての対策を整えていただきたいという思いから、今月は「インフルエンザの怖さ」についてご説明したいと思います。
【1】冬に流行する感染症
■新興感染症にも注意が必要■
感染症がなぜ冬に流行するのか、その背景を理解することが、感染症対策の第一歩です。まず、冬は乾燥して気温が低いため、感染症のウイルスは長く生存します。一方で、人は寒くなると代謝機能が低下し、それに伴い免疫力も下がるため、ウイルスに感染しやすくなります。
そして、空気が乾燥していると、ウイルスの水分が蒸発して比重が軽くなり、空気中に浮遊しやすくなるため、人から人への伝播が起こりやすくなります。さらに、冬にはインフルエンザのほか、RSウイルスやマイコプラズマ肺炎などの呼吸器感染症、ノロウイルスやロタウイルスなどによる感染性胃腸炎など、さまざまな感染症が流行します。
忘れてならないのは、新型コロナウイルスをはじめとする新興感染症も冬に流行していることです。21世紀に入って、新しく発生した新興感染症としては、重症呼吸器症候群(SARS)や中東呼吸器症候群(MERS)があり、新型コロナウイルスを含めて、発生当初は未知の感染症として対応策が定められず、その間に感染者が急増しました。ウイルスの変異によって、新興感染症が再び流行する危険性があることも、心に留めておきましょう。
【2】インフルエンザの怖さ
現在国内で流行している季節性インフルエンザのウイルスは、A(H1N1)亜型、A(H3N2)亜型とB型(ビクトリア系統)です。流行しやすい年齢層はウイルスの型によって多少異なりますが、今年もすべての年代の方がインフルエンザに注意する必要があります。
■強い感染力■
インフルエンザウイルスの感染経路は、飛沫感染(ひまつかんせん)と接触感染の2つがあります。
飛沫感染とは、感染者のくしゃみや咳、つばなどの飛沫と一緒にウイルスが放出され、別の人がそのウイルスを口や鼻から吸い込み感染することです。
接触感染とは、感染者がくしゃみや咳を手で押さえ、その手で周囲の物に触れることでウイルスが付着し、別の人がその物に触ってウイルスが手に付着し、その手で口や鼻に触れることで粘膜から感染することです。
インフルエンザウイルスは「モノ」の表面上で生存し、人への感染力があるのは2~8時間程度と言われており(米国CDCの資料より)、タイトル下の画像のように電車の手すり、つり革や公衆トイレのドアノブなどにウイルスが残っている状態で触り、その後手を洗わずに口や鼻の粘膜に触れると、感染してしまう可能性があります。
■合併症~インフルエンザ脳症や肺炎~■
インフルエンザで特に注意が必要なのは、高齢者の肺炎と小児の急性脳症です。他にもウイルス性肺炎、細菌性肺炎、中耳炎、筋炎、心筋炎、熱性けいれん等を合併することがあります。
インフルエンザ脳症は、発熱後1日以内にけいれんと意識障害が出現し、おくれて全身の臓器障害が現れ、続いてショック・心肺停止となり死亡します。主に5歳以下の乳幼児に発症し、30%が死亡、25%が後遺症を残すとされています。後遺症なく回復するのは約4割にとどまり、極めて重篤な合併症です。
二次性細菌性肺炎は、インフルエンザで傷んだ肺にさらに別の細菌が感染して起こる肺炎です。インフルエンザの治療だけでは改善せず、入院や死亡の原因になります。インフルエンザの症状が改善した後に再び症状が現れたり、3〜5日経っても症状が改善しない場合は、二次性細菌性肺炎を疑いましょう。高齢者では発症率が高いとされているため、特に注意が必要です。
【3】事業場としての対応
感染症対策の基本は「感染源の除去」「感染経路の遮断」「抵抗力を高める」の3つです。
■ワクチン接種■
事業所内で感染を広げず、重症化を防ぐためには、インフルエンザに対する抵抗力を高めるワクチン接種が有効です。個人個人がインフルエンザを発症しないよう、12月中旬までにワクチン接種を受けましょう。
現行のインフルエンザワクチンは、接種すればインフルエンザに絶対にかからない、というものではありません。しかし、インフルエンザの発病を予防することや、発病後の重症化や死亡を予防することに関しては、一定の効果があるとされています(国内の研究によれば、65歳以上の高齢者福祉施設に入所している高齢者については34~55%の発病を阻止し、82%の死亡を阻止する効果があったとされています)。
■感染者の早期発見・早期処置■
9月になったら、事業所の入口に体温測定装置を設置し、従業員だけでなく社内に出入りするすべての人の発熱チェック(検温)は行うようにしましょう。
また、洗面所では感染源を除去できるように、石けんを使って流水で15秒以上の手洗いを行いましょう。洗った後は、水分を十分に拭き取ることが重要で、使い捨てのペーパータオルを備え、その後に使用する速乾性擦式消毒用アルコール製剤(アルコールが 60~80%程度含まれている消毒薬)は、アルコールが完全に揮発するまで両手を擦り合わせることがポイントです。
38℃以上の発熱、咳、全身倦怠感等のインフルエンザの症状がみられたり、病院で感染していることが判明すれば、感染経路を遮断するため、5日間は出勤を停止し、他の人への感染が広がらないようにしましょう。
職場で感染者が出た後は、通常の清掃に加え、水と洗剤を使って、特に机やドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン、トイレの流水レバー、便座など、人がよく触れる場所は1日1回は拭き取り清掃を行い、感染源を除去しましょう。
【4】インフルエンザで参考になるサイト
厚生労働省 インフルエンザ(総合総合ページ)
厚生労働省では新型インフルエンザと季節性インフルエンザを合わせて、インフルエンザに関する発生状況などの最新情報や、医療機関向け・自治体向けの情報をサイトで公開しています。インフルエンザ対策を啓蒙するパンフレットのダウンロードも可能で、新型インフルエンザ対策のための行動計画やガイドラインを掲載している内閣官房のページなどもリンクされています。
東京都感染症センター インフルエンザ
東京都感染症センターでは東京都のインフルエンザの流行状況を、419か所(2025年8月現在)のインフルエンザ定点医療機関から報告に基づき公表しています。東京都の市区町村ごとの地図で、どこで患者が増えているかを地域単位で把握でき、周辺自治体の流行状況も首都圏の患者報告数のグラフで確認できます。
内閣府 政府広報オンライン インフルエンザの感染を防ぐポイント
NHK 感染症データと医療・健康情報 約20種類の感染データ・情報
YouTubeチャンネル「関谷剛の産業医こぼれ話」 2025年9月『インフルエンザ』
医師・産業医の関谷剛先生が、この通信と同じテーマについて解説した動画を毎月公開しております。文章だけでは伝わりにくい、病気予防のポイントや産業医としての経験談などを自らの言葉で説明しています。YouTubeチャンネルで御覧頂けますから、事業所でもご家庭でもぜひ御覧下さい。
あとがき
社内で感染者が出ていなくても、学校や地域で患者が発生し始めた場合は、急速に感染が広がる可能性があります。また、インフルエンザのタイプによって治療方法が異なりますので、ぜひ産業医にご相談ください。(産業医 関谷剛)